国内市場においては為替の影響もあると思いますが年々スマホが高価格化しており数年前はミドルレンジが5万円前後だったのが今や8万円を超えてきておりかなり高くなったと思います。
一方で全体的に高価格化しているとはいえ存在が引き立っているのが中華スマホかなと思います。今回はXiaomiにOppoにvivoなど中華スマホを購入する前に確認してほしいことについて主観的にまとめたいと思います。。
何より価格を優先。
 まず今回の記事では政治的リスクなどは考慮せず単純にスマホとしてどうなのかとしてみます。よくセキュリティ関連を懸念する声を聞ききますが今まで頂いたコメントを見ると単純に手持ちのスマホのセキュリティアップデートがきれた状態で使っている人が懸念の声をあげている印象を受けます。
まず今回の記事では政治的リスクなどは考慮せず単純にスマホとしてどうなのかとしてみます。よくセキュリティ関連を懸念する声を聞ききますが今まで頂いたコメントを見ると単純に手持ちのスマホのセキュリティアップデートがきれた状態で使っている人が懸念の声をあげている印象を受けます。
中華なら危険でそれ以外は安全と考えるべきではなく、まずは自分のスマホのサポート期間がいつまでか把握した上で最新のセキュリティ状態にした上で使うのが最優先なのかなと思います。
その上で一つ目としてはコストカットのためにローカライズをカットしていることが増えてきた印象を受けます。国内で販売台数を伸ばすにはキャリアに取り扱ってもらう必要がありキャリアに扱ってもらうにはおサイフケータイなどローカライズを完璧にしておくのが最低限の条件という感じになります。
ただ当たり前の話ですがローカライズするにもコストがかかり結果本体価格にも影響します。
 Xiaomiによるとローカライズを完璧にした状態でXiaomi 15を国内で発売するとなったら15万円近くの価格設定になるとの話でしたが実際には直販版のみとはいえ12万円ちょいです。
Xiaomiによるとローカライズを完璧にした状態でXiaomi 15を国内で発売するとなったら15万円近くの価格設定になるとの話でしたが実際には直販版のみとはいえ12万円ちょいです。
あくまでもどんぶり勘定という感じですがローカライズをするかしないかで2万円近く違います。そしてローカライズを完璧にしてキャリアに扱ってもらったとしてもキャリア価格はさらに高くなる可能性があります。
そうなると中華系の安いというイメージは完全になくなる可能性がありむしろデメリットになるのかもしれません。
コストが増す理由。
 ちなみにローカライズしてコストが増加する理由としておサイフケータイのためのFelicaを搭載とハード的な変更もあれば日本専用のファームウェアを準備する必要があることも要因です。
ちなみにローカライズしてコストが増加する理由としておサイフケータイのためのFelicaを搭載とハード的な変更もあれば日本専用のファームウェアを準備する必要があることも要因です。
また日本向けのファームウェアにもアップデートを提供しなければいけないので余計にコストがかかります。ただ技適はもちろん通すとしてもそれ以外をグローバルと共通化することでソフトもハードもコストを下げることができ本体価格を出来るだけ安く提供できるというメリットがあります。
そしてローカライズは大きく対応バンドとおサイフケータイの2つでおサイフケータイの有無がよく話題になりますが多種多様な電子決済が提供されていることからも以前と状況が違います。
個人的にはおサイフケータイなしの端末を使う場合はPixel Watchでカバーするので問題ないです。ここはユーザーのライフスタイルに強く紐づいているのでどっちが正解ということはないと思います。
ただスマートウォッチやサブ機などで電子決済をカバーできる人からすればローカライズの影響で本体価格が高くなるのはむしろマイナスに感じる可能性があり逆にiPhoneやGalaxyの無印は13万円弱ですがローカライズをやめれば11万円前後ともっと安くなる可能性もあるのかもしれません。
マーケティングが巧妙。
 次に2つ目としてマーケティングで中華メーカーはプロモーションが非常に上手いと思います。言い方が悪いかもしれませんが分かりやすいスペックを過剰にアピールすることが多いです。
次に2つ目としてマーケティングで中華メーカーはプロモーションが非常に上手いと思います。言い方が悪いかもしれませんが分かりやすいスペックを過剰にアピールすることが多いです。
数年前でみればカメラの画素数でいまだに画素数が高いほどいいカメラだと思っている人もいます。またカメラセンサーの数が多ければカメラが強いというイメージにしたのも中華メーカーです。
そのためマクロ用のセンサーを含めてトリプルレンズカメラ構成とか間違ってはないけど実用的な部分でみるとちょっと違うという感じで分かりやすいスペックに釣られるべきではないと思います。
カメラに関してもいいカメラであるかどうかの要素の一つとして画素数があることに違いはないです。ただ画素数だけでカメラの良し悪しが決まるわけではなく良し悪しをスペックだけでは判断することはかなり難しいです。
ベンチマークを鵜呑みにする。
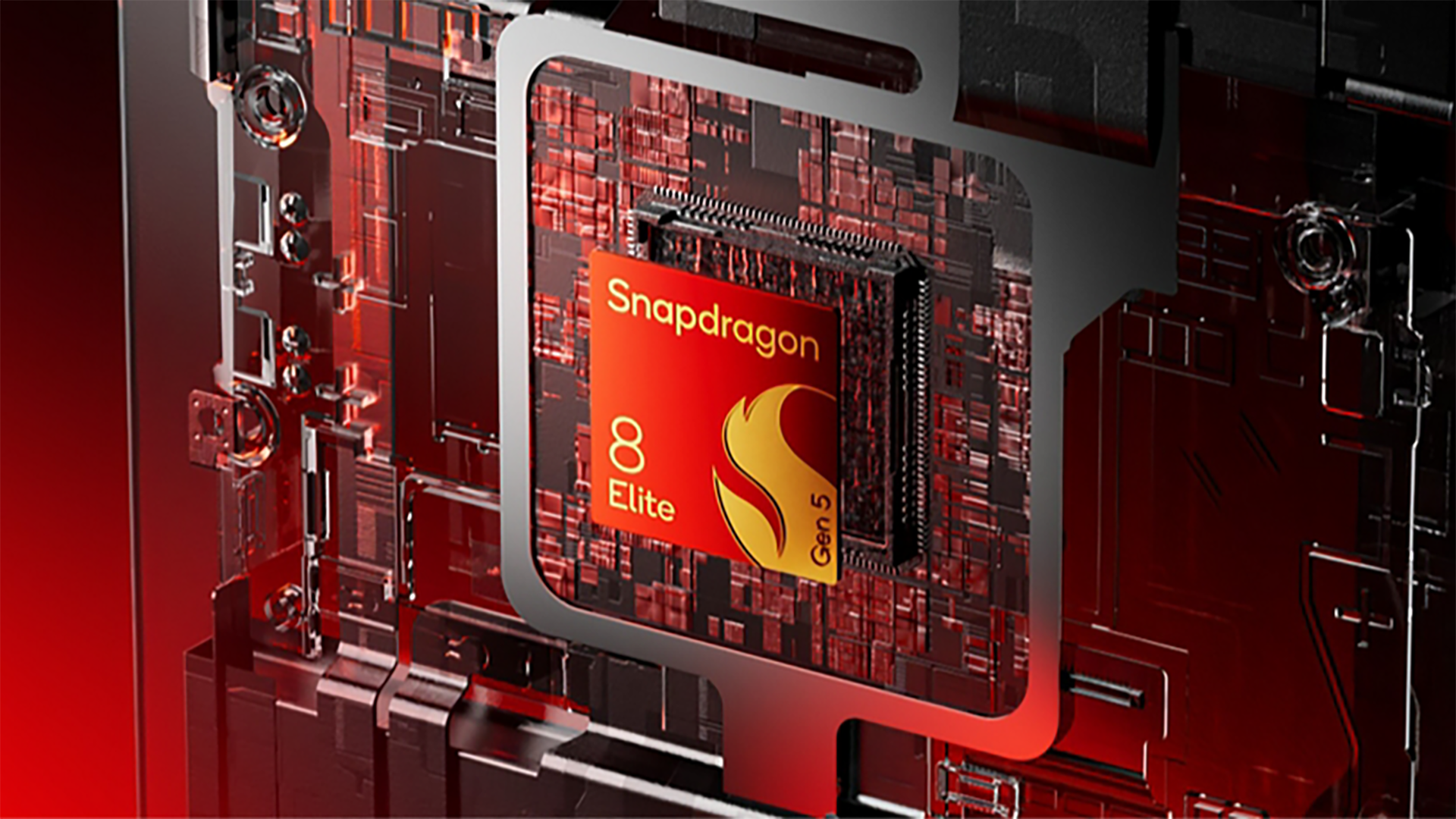 そして最近でみるとPixelを機に話題となっているのがベンチマークですが同様だと思います。Snapdragon 8 Elite Gen 5やDimensity9500をみるとAnTuTuで400万点オーバーです。
そして最近でみるとPixelを機に話題となっているのがベンチマークですが同様だと思います。Snapdragon 8 Elite Gen 5やDimensity9500をみるとAnTuTuで400万点オーバーです。
ちなみにSnapdragon 8 Eliteの世代は300万点がが最高クラスだったので僅か1年で100万点もスコアが伸びたことになりますがスコアに比例してユーザーの使い方は変わらないです。
そしてスコアが伸びたからといって動作性も比例して快適になるかと言われれば微妙です。もちろん負荷が高いゲームであれば高性能のGPUを搭載したことで今まで以上に滑らかになるかしれません。
一方で日常使う上において閾値はかなり前に突破しているのでスコアの差を実感するのが難しいと思います。結局スコアが100万点の機種と400万点の機種を日常使いで比較しても差を実感しにくいと思います。
 むしろ同じSoCだとしてもリフレッシュレートが60Hzと120Hzの方が違いが分かりやすいかもです。ベンチマークは指標としては優秀だと思いますが絶対ではなく割と鵜呑みにしている人が多いです。
むしろ同じSoCだとしてもリフレッシュレートが60Hzと120Hzの方が違いが分かりやすいかもです。ベンチマークは指標としては優秀だと思いますが絶対ではなく割と鵜呑みにしている人が多いです。
ここ数年トレンドになっているAIに関して使わないとの声も聞きますがAIでかこっているだけでざっくりいえばただの新機能に過ぎないので逆に言えば新機能を使うユーザーは割と少ないです。
このことを考えると例えばベンチマークスコアが高い機種を購入したとしても使い方自体は大きく変わらない人の方が多いと思っておりベンチマークスコアを気にするのであればその機種の発熱対策や電池持ちやカメラなど実用的な部分を重視したほうが合理的だと思います。
シリコンカーボンバッテリー。
 そして3つ目としてはプロモーションの話と重複しますがバッテリー容量も注意が必要です。直近でみればXiaomi 17シリーズやOppo Find X9シリーズなど7000mAh超えが当たり前です。
そして3つ目としてはプロモーションの話と重複しますがバッテリー容量も注意が必要です。直近でみればXiaomi 17シリーズやOppo Find X9シリーズなど7000mAh超えが当たり前です。
むしろvivo X300シリーズの6000mAhちょいとスペック的にはかなり見劣りしている印象です。ただGalaxyやPixelであれば5000mAh前後であることを考えると圧倒的な差があります。
少なくともバッテリー容量でみれば圧倒的ですが品質自体はそこまで良くないと言われています。バッテリーは充電を繰り返せば劣化が進み満充電容量が徐々に下がっていくのが常です。
例えばEUの規則でみると800回の充電サイクル後に満充電容量が80%以上を維持することを規定しています。一方でシリコンカーボンバッテリーは600回前後で80%以下になると言われているので劣化が早いです。
また今年登場した大容量機種は単純に考えればシリコン含有量が増えている可能性があります。つまりバッテリー容量は立派でも劣化自体はPixelやiPhoneと比較するとかなり早い可能性があります。
 ちなみにGalaxy Z Fold7は前モデル対比でバッテリー容量が変わらなかったのは残念な所です。ただ品質を重視しており2000回の充電サイクル後でも満充電容量を80%維持するとの話です。
ちなみにGalaxy Z Fold7は前モデル対比でバッテリー容量が変わらなかったのは残念な所です。ただ品質を重視しており2000回の充電サイクル後でも満充電容量を80%維持するとの話です。
またバッテリー容量に対してシリコンカーボンバッテリーは電力効率が悪いとの指摘もあります。もちろんバッテリー容量という絶対的な部分があるので少ないよりは多い方がいいと思います。
単純に比較は出来ませんが例えば4685mAhのバッテリーを搭載したiPhone 16 Pro Maxは海外サイトのバッテリーテストにおいて17時間18分に対して5410mAhのXiaomi 15 Ultraが16時間13分で6100mAhのOppo Find X8 Ultraは16時間26分とiPhone 16 Pro Max以下です。
電池持ちを決める要素の一つとしてバッテリー容量は重要ですがSoCやOSにチューニングなど様々な要素の組み合わせで決まることでありバッテリー容量が多ければいいわけではないです。
むしろ長期的な利用を考えている人からすれば劣化が早いのは大きなデメリットになる可能性があります。また少し前であればディスプレイ輝度を過剰にアピールする傾向にありましたが落ち着いた感じです。
分かりやすいスペックほど注目を集めやすいですが表面的な部分では分からないので注意が必要です。
ソフトよりハード。
 最後に4つ目として完全に主観ですがソフトよりもハードに拘る人向けなのかなと思います。もちろん好みがあると思いますが中華系の機種は大陸版の方が色々と充実していることが多いです。
最後に4つ目として完全に主観ですがソフトよりもハードに拘る人向けなのかなと思います。もちろん好みがあると思いますが中華系の機種は大陸版の方が色々と充実していることが多いです。
言語対応の問題なのか規制の問題なのか不明ですが特にAIの対応で地味に差がある印象を受けます。またAndroidをベースにしているとはいえ独自UIを採用しているためメーカーによって癖があります。
自分はソフトにあまり拘りがないので気にならないですがカスタマイズ性であればGalaxyでエコシステムであればiPhoneとソフトというか使いやすさを求めるならこの2択という感じです。
一方で中華系のフラッグシップモデルの醍醐味とも言えるのがハードでゴリ押ししてくれることだと思います。先ほどの話とも重複しますがハードが強ければ全部が強いわけじゃないとはいえロマンがあります。
カメラが強い。
 特にカメラに少しでも拘るユーザーにとって中華系を一度は触ってほしいのかなと思います。個人的にはフラッグシップの無印ではなく最低でもProモデルは一度触ってほしいところです。
特にカメラに少しでも拘るユーザーにとって中華系を一度は触ってほしいのかなと思います。個人的にはフラッグシップの無印ではなく最低でもProモデルは一度触ってほしいところです。
そして海外スマホに抵抗がない人であれば各社のUltraモデルは一度触ってほしいところです。ちなみに国内でみればXiaomi 15 Ultraが有力な選択肢でメインカメラセンサーにLYT-900で望遠に1/1.4インチのHP9とGalaxyやiPhoneから見れば超大型センサーを搭載しています。
中華系のUltraモデルは大陸版のみであることが多くXiaomiはむしろかなり頑張ってくれている方だと思います。そしてXiaomiを触ってみて面白いと思う人はOppo Find X8 Ultraやvivo X200 Ultraを一度触ってみるのもありかなと思っており現状スマホカメラの頂点になっているのかなと思います。
もちろんハード全体でみた時に強いですがGalaxyやiPhoneのようなバランス型ではなくカメラ特化型に近い機種でカメラに強い分使いやすさを多少妥協する必要があるかなと思います。
ユーザーによってはバランス型の方がいいと思いますが高いお金を出すのであれば何かに特化した機種の方がいいと思うユーザーにとって中華メーカーは魅力的な選択肢だと思います。
まとめ。
 今回は中華メーカーの機種を購入する前に確認してほしいことについて簡単にまとめてみました。中華系はよくコスパがいいと言われますが個人的にはコスパがいいと言われない中華スマホの方がいいと思っており価格関係なく欲しいと思わせてくれる機種の方が絶対使ってみて楽しいと思います。
今回は中華メーカーの機種を購入する前に確認してほしいことについて簡単にまとめてみました。中華系はよくコスパがいいと言われますが個人的にはコスパがいいと言われない中華スマホの方がいいと思っており価格関係なく欲しいと思わせてくれる機種の方が絶対使ってみて楽しいと思います。











