中華メーカーのマーケティングが上手かったと捉えるべきなのか何ともですが、スマホのパフォーマンスの指標の一つとしてAnTuTuのベンチマークスコアが採用されることが多いです。
もちろん指標の一つしては重要だと思いますが、「ベンチマーク至上主義」の人が圧倒的に多いことも事実です。だからこそかGoogle Pixel 10シリーズはベンチマークスコアが低いことからも余計に叩かれている印象を受けます。
今回Phone ArenaによるとSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載機種の全てが発熱に対処できているわけではないと報告しているのでまとめたいと思います。
発熱がすごい。
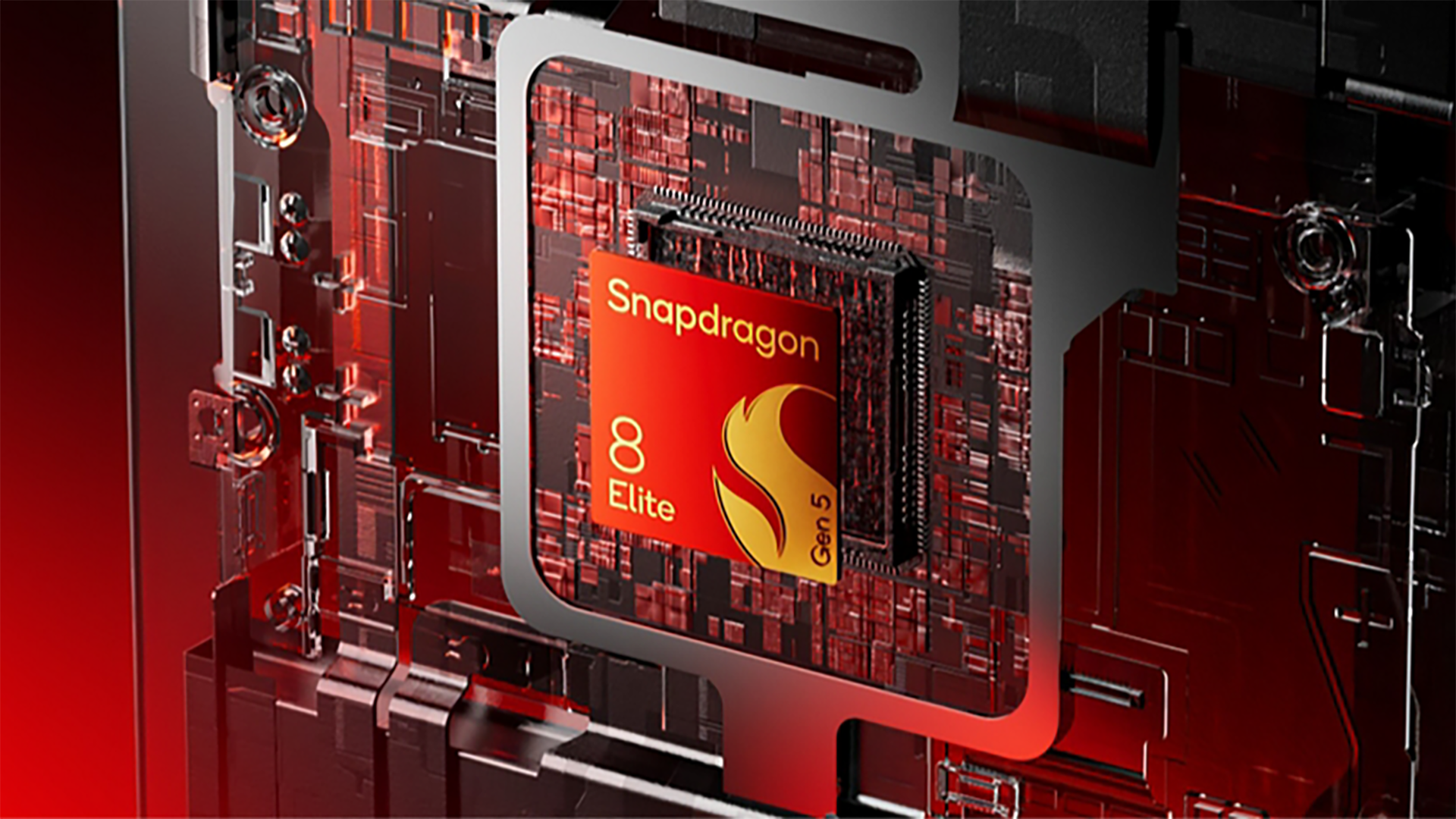
まず同サイトによるとSnapdragon 8 elite Gen 5を搭載した「RedMagic 11 Pro」をテストしたことに言及。その結果あらゆる点でiPhone 17 Proシリーズが搭載しているA19 Proを上回っていたとしています。
そしてRedMagic 11 Proが高いパフォーマンスを発揮できた理由としては超強力な冷却システムにあるとしています。RedMagic 11 Proではなのセラミックポンプを備えた液体冷却構造に加え、超巨大なベイバーチャンバーにアクティブファンまで搭載しており、スマホの中では圧倒的な発熱対策を実装しているとしています。
一方で同じNubiaの製品であるNubia Z80 Ultraに関しては以下のようにコメントしています。
結果ははるかにお世辞ではありませんでした。電話は触ると不快に熱くなり、内部は50°Cを超え、最高のパフォーマンスを維持するのに苦労しました。初の数回のパスの間、電話はなんとか良いピークパフォーマンスを保持しましたが、気温が上がるにつれて、物事は急速に悪化しました。テスト終了までに、パフォーマンスは50%以上低下しました。
あくまでもNubia Z80 Ultraでの結果になりますが、同サイトによると結果的にはSnapdragon 8 Eliteのスコアよりも悪化しており、パフォーマンスの持続性という部分ではSnapdragon 8 Gen 3搭載機種よりも悪い場合もあると指摘しています。
ベンチマークの高さはユーザビリティに直結しない。

少なくともSnapdragon 8 Elite Gen 5にしろDimensity9500にしろパフォーマンスが高い一方で消費電力も多く発熱もしやすいことになります。そのためパフォーマンスを最大限発揮しつつ持続性を意識するとなった時にRedMagic 11 Proのような強力な冷却システムが必要になるのかもしれません。
一方でベンチマークがハイスコアを獲得できるようなチューニングをすると表面上のスコアは良くても持続性も悪ければ発熱もひどいとベンチマークスコアが高くなればなるほど反比例してユーザビリティが下がる可能性があります。
このことを考えると発熱対策をより強化するのが厳しい場合、例えばXperiaのように「最適化」を優先してハイスコアを優先しない。もしくはGoogleは極端にも感じますが、閾値を設定してそれ以上のパフォーマンスは後回しにして、発熱抑制や電池持ちにAIなどを優先する感じになるのかも。
来年登場する最新SoCはさらにコストが高いと予測されています。コストが高くて爆熱でユーザビリティが低いとなれば笑えないので、今後メーカーはSoCと向き合い方が変わってくるのかなと思います。










